寝酒 ナイトキャップ お酒 についてのガイド 安眠効果を高める「寝酒」の選び方について紹介します。ナイトキャップを推奨している情報もあれば、絶対ダメ!という情報も目にします。実際、安眠できなくなってしまった際に上手に活用すれば ナイトキャップ お酒 の効果に関してデメリットもありますが、メリットの安眠効果に期待できそうです。
寝酒 ナイトキャップ お酒 についてのガイド

はじめに:ナイトキャップを始めたいあなたへ
- ナイトキャップが注目される理由
- この記事で得られること(安眠効果を高めるお酒の選び方、飲み方、注意点など)
- そもそも「ナイトキャップ」とは?
- ナイトキャップの語源と文化
- お酒が睡眠に与える影響(アルコールのメリット・デメリットを科学的に解説)
- 【安眠効果UP】ナイトキャップに最適なお酒の選び方
- ポイント1:度数が高すぎないもの
- 高アルコールが睡眠を妨げる理由
- ポイント2:リラックス効果のある成分に着目
- トリプトファン、GABAなど、安眠をサポートする成分を含むお酒を紹介
- ポイント3:香りや味で選ぶ
- ハーブ系、スパイス系など、リラックス効果のある香りの重要性を解説
- ポイント1:度数が高すぎないもの
- 【種類別】ナイトキャップにおすすめのお酒5選
- ワイン(特に赤ワイン):ポリフェノールとリラックス効果
- ブランデー:香りによるリラックス効果
- リキュール:ハーブ系リキュールの活用法
- ウイスキー:シングルモルトなどの香りの良さ
- ホットカクテル:体を温める効果のあるレシピを紹介
- 効果を台無しにしない!ナイトキャップの正しい飲み方
- 飲むタイミング(就寝の1~2時間前が理想)
- 飲む量(適量を守ることの重要性)
- チェイサー(水)の必要性
- 注意!ナイトキャップが逆効果になるケース
- 飲みすぎるとどうなるか(睡眠の質の低下、脱水症状など)
- 毎日飲むことの危険性(アルコール依存症リスク)
- ナイトキャップをやめるべき人(持病がある方など)
- まとめ:賢くナイトキャップを楽しもう
ナイトキャップが注目される理由
「寝酒」は、古くから親しまれている習慣ですが、近年再び注目されるようになった背景には、現代社会特有のいくつかの理由が考えられます。
1. 睡眠の悩みを持つ人の増加
- ストレス社会:現代社会は、仕事や人間関係、情報過多などによるストレスで、精神的な緊張状態が続きやすい環境です。これにより、なかなか寝付けない、眠りが浅いといった睡眠の悩みを抱える人が増えています。
- 手軽な解決策としての認識:「寝酒をすれば眠れる」という経験から、睡眠導入剤など医療機関への受診に抵抗がある人にとって、手軽な自己解決策として選ばれがちです。
2. リラックス効果への期待
- GABA(ギャバ)との関連性:アルコールには、脳の神経伝達物質であるGABA(ガンマアミノ酪酸)の働きを強化する作用があり、これによってリラックス効果や鎮静効果がもたらされます。この作用が、一時的に寝つきを良くする効果があるため、「寝酒」として重宝されます。
- 一日の終わりの儀式:疲れた一日の終わりに、お酒を飲むことで心身の緊張を解きほぐす「リラックスタイム」として、ナイトキャップの習慣が広まっています。
3. 健康志向トレンドとの融合
- 「ナイトキャップ」というおしゃれな響き:ただの「寝酒」ではなく、海外の文化的な習慣である「ナイトキャップ」という言葉を用いることで、おしゃれで洗練されたイメージが加わり、若い世代にも抵抗感なく受け入れられています。
- 美容や健康への意識:健康や美容への意識が高い層の間で、「質の良い睡眠」が美しさや健康に不可欠であるという認識が広まっています。その中で、安眠をサポートするアイテムの一つとして、ハーブ系リキュールやノンアルコール飲料など、様々な選択肢が生まれています。
しかし、これらの注目が高まる一方で、多くの専門家は寝酒のデメリットを指摘しています。
- 睡眠の質の低下:アルコールは入眠を促す一方で、分解される過程で生じるアセトアルデヒドには覚醒作用があり、夜中に目が覚めやすくなります。結果的に、眠りが浅くなり、睡眠の質を下げてしまうことがわかっています。
- 依存症リスク:寝酒を習慣化すると、アルコールなしでは眠れなくなる「アルコール性不眠症」に陥ったり、アルコール依存症に繋がるリスクがあります。
- 健康への影響:連日の飲酒は、肝臓への負担や様々な健康被害を引き起こす可能性があります。
このように、寝酒は手軽な解決策として注目される一方で、そのリスクも同時に認識することが重要です。このため、近年では、正しい知識に基づいた「賢い寝酒の選び方」や「ナイトキャップの楽しみ方」が求められるようになっています。
睡眠前の軽い飲酒は、西洋では「ナイトキャップ」とよばれ、適量であれば、快い睡眠の手助けになるとされています。アルコールは、血行がよくなり、心も解放されれば、入眠儀式としてこれほどいいものはないでしょう。日常のストレス解消にも一役買ってくれます。
ただ、日本人の中にはアルコール分解酵素をもたない、いわゆる下戸の人も少なくありません。こんな人は飲酒によってかえって睡眠できなくなるのでナイトキャップは当然おすすめできません。
そもそも「ナイトキャップ」とは?

寝酒(ねざけ)」とは、就寝前に酒を飲む行為、またはその際に飲む酒そのものを指します。英語では「ナイトキャップ(nightcap)」と呼ばれ、海外でも習慣として定着している国があります。
寝酒の目的は、一般的に「寝つきを良くする」「リラックスする」「ストレスを発散する」といったものです。アルコールには脳の神経細胞の興奮を抑える鎮静作用があるため、少量であれば一時的に眠気を誘う効果があるためです。
しかし、多くの専門家は、寝酒を習慣にすることに警鐘を鳴らしています。
寝酒の主なデメリット
- 睡眠の質の低下: アルコールは入眠を早める作用がある一方で、アルコールが分解される過程で眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなります。結果的に、深い睡眠であるノンレム睡眠が減少し、睡眠の質が低下します。
- 利尿作用による中途覚醒: アルコールには利尿作用があるため、夜中に尿意で目が覚めやすくなります。
- アルコール依存症のリスク: 寝酒を習慣化すると、アルコールがないと眠れないという状態に陥り、アルコール依存症になるリスクが高まります。
- 健康への悪影響: 毎日の飲酒は肝臓に負担をかけ、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。
このように、寝酒は一時的な解決策としては機能するかもしれませんが、根本的な睡眠の質を改善するものではなく、むしろ長期的に見ると健康を損なうリスクがあります。そのため、不眠に悩んでいる場合は、寝酒に頼るのではなく、専門医に相談するなど、適切な対処をすることが推奨されています。
ナイトキャップの語源と文化
日本では寝酒とナイトキャップを同じ意味で使用していますが2つの語源は異なります。
寝酒とナイトキャップの語源は異なる
寝酒の語源
「寝酒」は日本語の「寝る」と「酒」を組み合わせた言葉です。その名の通り、就寝前に眠りを誘うために飲む酒を指し、古くから日本で習慣として存在しました。特定の起源があるわけではなく、長い歴史の中で自然に生まれた言葉です。
ナイトキャップの語源
英語の「nightcap」は、元々、寝るときに頭に被る布製の帽子を指していました。これは、寒い夜に頭部を冷えから守るための防寒具として使われていました。
その後、人々が寝る前に体を温めるために飲む温かい飲み物(ブランデーやホットミルクなど)を「nightcap」と呼ぶようになりました。これは、体を温めて快適に眠るという目的が、帽子と同じであったことから転用されたとされています。
現在では、就寝前に飲むお酒全般を指す言葉として広く使われています。
【安眠効果UP】ナイトキャップに最適なお酒の選び方
ナイトキャップとしてお酒を楽しむなら、ただ酔うだけでなく、安眠効果をサポートする賢い選び方が大切です。ここでは、安眠効果を高めるための3つのポイントをご紹介します。

1. 度数が高すぎないものを選ぶ
アルコールには入眠を促す効果がありますが、度数が高すぎると逆効果になります。
- 高アルコール度数のお酒のデメリット:
- 分解に時間がかかり、中途覚醒や睡眠の質の低下を招きやすい。
- 利尿作用が強まり、夜中にトイレで目が覚める原因になる。
- おすすめの選択肢:
- 低アルコールリキュールやワインなど、度数が10〜15%程度のものが適しています。
- アルコール度数が高いお酒(ウイスキー、ブランデーなど)を飲む場合は、水や炭酸水で割って飲むようにしましょう。
2. リラックス効果のある成分に着目する
お酒の種類によっては、安眠をサポートする成分が含まれているものがあります。
- ワイン(特に赤ワイン):
- ポリフェノール: 抗酸化作用に加え、血管を広げて血行を良くする効果が期待できます。体が温まり、リラックスしやすくなります。
- メラトニン: 赤ワインには、睡眠ホルモンであるメラトニンが含まれているという研究もあります。
- ハーブ系リキュール:
- カモミール、ラベンダー、レモンバームなどのハーブを原料としたリキュールは、その香りにアロマテラピー効果があり、精神を落ち着かせる効果が期待できます。
3. 香りや味で選ぶ
五感に訴えかけるリラックス効果も重要です。
- ブランデー、ウイスキー:
- 複雑な香りは、アロマテラピー効果をもたらし、心地よいリラックスタイムを演出します。香りをゆっくりと楽しむことで、自然と気持ちが落ち着きます。
- ホットカクテル:
- ホットワインやホットミルクにリキュールを加えるなど、体を温める飲み方は特におすすめです。体が温まると、就寝時に自然と体温が下がり、眠りに入りやすくなります。
まとめ
ナイトキャップは、「少量」「低アルコール」「リラックス成分」を意識して選ぶことが大切です。くれぐれも飲みすぎには注意し、自分に合ったお酒を見つけて、心身ともにリラックスする時間を楽しんでください。
【種類別】ナイトキャップにおすすめのお酒5選
ナイトキャップにおすすめのお酒は、リラックス効果が高く、少量でも満足感が得られるものが理想です。ここでは、種類別に5つのお酒とその楽しみ方をご紹介します。
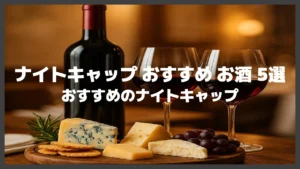
1. ブランデー
芳醇な香りが特徴のブランデーは、ゆっくりと香りを楽しみながら飲むことで、心身を落ち着かせる効果が期待できます。
- 楽しみ方: ストレートで少量ずつ、またはお湯割り(ホットブランデー)にして体を温めるのも良いでしょう。
- ポイント: 寒い季節には、ホットブランデーに蜂蜜やレモンを加えると、さらにリラックス効果が高まります。
2. ウイスキー
ウイスキーもまた、豊かな香りが魅力です。特にシングルモルトなど、香りにこだわったものを選ぶのがおすすめです。
- 楽しみ方: ロックやストレートで少しずつ味わうのが一般的ですが、ホットウイスキーにすることで体が温まり、よりリラックスできます。
- ポイント: 香りを最大限に楽しむために、グラスを温めてから注ぐのもおすすめです。
3. ハーブ系リキュール
ハーブの香りは、アロマテラピー効果があり、安眠をサポートしてくれます。
- 楽しみ方: ハーブ系リキュールは、ハーブティーやホットミルクで割って飲むのがおすすめです。ノンアルコールでも代用できるため、アルコールが苦手な方にも適しています。
- ポイント: ラベンダーやカモミール、セージなどを原料としたリキュールを選ぶと、よりリラックス効果が高まります。
4. 赤ワイン
赤ワインに含まれるポリフェノールは、抗酸化作用だけでなく、血管を広げて血行を良くする効果も期待できます。
- 楽しみ方: 寝る前にグラス一杯をゆっくりと味わうのが理想です。
- ポイント: ホットワインにすれば、スパイス(シナモン、クローブなど)の香りでリラックス効果がさらに高まります。
5. ホットカクテル
体を温めることが、良質な睡眠につながります。ナイトキャップには、体を内側から温めるホットカクテルも最適です。
- 楽しみ方: ホットウイスキーやホットブランデー、ホットワインはもちろん、ホットミルクにリキュールを加えるなど、様々なアレンジが楽しめます。
- ポイント: 寝る前の胃への負担を減らすため、甘すぎないレシピを選ぶようにしましょう。
これらの飲み方を参考に、自分に合ったナイトキャップを見つけて、心地よい眠りにつくための習慣にしてみてください。
効果を台無しにしない!ナイトキャップの正しい飲み方
ナイトキャップの効果を最大限に引き出し、安眠を妨げないための正しい飲み方と注意点をまとめました。せっかくのリラックスタイムを台無しにしないよう、以下のポイントを押さえましょう。

1. 飲むタイミングは「就寝の1~2時間前」がベスト
- なぜ?:アルコールを摂取すると、肝臓がアルコールを分解し始めます。この分解中に発生するアセトアルデヒドには覚醒作用があるため、就寝直前に飲むと、深い眠りを妨げてしまう可能性があります。
- 理想のタイミング:ベッドに入る1~2時間前にナイトキャップを済ませ、体がアルコールを分解する時間を確保しましょう。これにより、アルコールの鎮静作用が効きつつ、分解の影響で目が覚めるのを防げます。
2. 飲む量は「少量」を厳守する
- なぜ?:アルコールは、少量であればリラックス効果をもたらしますが、飲みすぎると睡眠の質を著しく低下させます。また、アルコール依存症のリスクも高まります。
- 理想の量:ワインならグラス1杯、ウイスキーやブランデーならシングル(30ml)程度に留めましょう。心地よい眠りを誘うには、多量に飲む必要はありません。
3. 「チェイサー(水)」を必ず用意する
- なぜ?:アルコールには利尿作用と脱水作用があります。水分が不足すると、喉の渇きで夜中に目が覚めてしまう原因になります。
- 理想の飲み方:お酒を一口飲んだら、チェイサーの水を一口飲む、というように交互に飲むことを心がけましょう。これにより、脱水を防ぎ、翌朝の二日酔いも軽減できます。二日酔いにならないための水の飲み方 悪酔いを避ける水の飲み方
4. 「ホットドリンク」で体を温める
- なぜ?:人間は、体温が下がると眠くなる性質があります。就寝前に温かい飲み物を飲むと、一時的に体温が上がり、その後ゆっくりと下がっていくことで、自然な眠りにつきやすくなります。
- 理想の飲み方:ホットワインやホットウイスキー、ハーブティー割りなど、体を温める飲み方を選ぶのがおすすめです。
5. 「食事のすぐ後」は避ける
- なぜ?:満腹の状態でお酒を飲むと、胃腸に負担がかかり、消化不良を起こしやすくなります。
- 理想のタイミング:夕食を終えてから1時間ほど経って、消化がある程度落ち着いてからナイトキャップを楽しみましょう。
これらの正しい飲み方を守ることで、ナイトキャップを健康的な習慣として楽しむことができます。くれぐれも、多量飲酒や毎日の習慣化には注意し、心身のリラックスを目的とした質の高い時間を過ごしてください。
注意!ナイトキャップが逆効果になるケース
ナイトキャップは、適切に楽しめばリラックスできる習慣ですが、飲み方や体調によっては逆効果になることがあります。安眠を妨げたり、健康を害したりするリスクを避けるため、以下の点に注意しましょう。

1. 飲みすぎると睡眠の質が低下する
「酔って眠ればぐっすり眠れる」と考えがちですが、それは大きな誤解です。
- 入眠は早いが、途中で目が覚める:アルコールには鎮静作用があるため、一時的に眠気を誘います。しかし、体内でアルコールが分解される過程で、覚醒作用を持つアセトアルデヒドが生成され、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりしやすくなります。
- 睡眠サイクルを乱す:アルコールは、脳と体を休ませるための重要な睡眠段階であるレム睡眠やノンレム睡眠を妨げます。結果として、いくら長く眠っても疲れが取れない「睡眠の質の低下」につながります。
2. 毎日の習慣化はアルコール依存症のリスクを高める
ナイトキャップを毎晩飲む習慣は危険です。
- 「飲まないと眠れない」状態に:アルコールに頼って眠る習慣が定着すると、アルコールなしでは眠れない「アルコール性不眠症」に陥ることがあります。
- 依存症へ進行する恐れ:睡眠のためにお酒を飲む量が増えていき、最終的にはアルコール依存症に発展するリスクが高まります。
3. 持病がある人は飲むべきではない
以下のような持病がある方は、ナイトキャップを控えるべきです。
- 睡眠時無呼吸症候群:アルコールは筋肉を緩める作用があるため、気道が狭くなり、症状を悪化させる可能性があります。
- 肝臓病:アルコールは肝臓で分解されるため、すでに肝臓に疾患がある場合は大きな負担をかけてしまいます。
- 精神疾患:うつ病や不安障害などの治療薬を服用している場合、アルコールとの相互作用で、薬の効果が弱まったり、副作用が強く出たりする可能性があります。
4. 脱水症状を引き起こす可能性がある
アルコールには利尿作用があり、体内の水分を外に出してしまいます。
- 喉の渇きで目が覚める:水分が不足すると、夜中に喉の渇きで目が覚め、睡眠が中断されます。
- 翌朝の不調:脱水症状は、頭痛やだるさなど、翌朝の二日酔いの原因の一つとなります。
ナイトキャップは、あくまで特別な日のリラックスタイムとして、少量のお酒をたまに楽しむ程度に留めるのが賢明です。もし「飲まないと眠れない」と感じたら、専門医に相談するなど、適切な対処を検討してください。
最後に
ナイトキャップを習慣化しない
寝つきが悪いという理由で、毎晩のようにナイトキャップを口にする習慣は、あまりおすすめできません。
アルコールを飲むと、たしかにフワッと気持ちよくなって眠りやすそうですが、アルコールの作用はあくまでも入眠作用だけのものになります。
そのあとは、アルコールは体内から水分を蒸発させるため、真夜中になってのどが乾いたり、あるいは何度もトイレにいきたくなって目が覚めたりと、必ずしもぐっすり眠れる状態にはならないのです。
また、アルコールはレム睡眠を減らしたり、睡眠リズムの乱れが生じます。血中のアルコール濃度が減少してくる際にはアルコールの覚醒作用が働いて眠りが浅くなるのも熟睡の妨げになります。
「どうしても今日は寝つけない」という特別な場合はのぞき、習慣化するのを避けましょう。
睡眠薬がわりに使うのなら副作用のない「快眠ぐっすり酵素「セロトアルファ」がおすすめです。飲むだけで眠ることができます。常習性もなく安心です。
お酒については、睡眠との関連性ではさまざまですが、寝酒も「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」という記事がわかりやすく記載されています。
そして、最近の研究では少量のアルコールでも睡眠に対しては害が多いという考え方になっています。
ナイトキャップ用のカクテル(自分で作るのも楽しいかも?)
ナイトキャップとして飲むお酒は、たいていは市販のブランデーやリキュールになりますが、たまには自分でつくってみるのも楽しくなります。
昔から有名なナイトキャップ用のカクテルとして、『ホットエッグノッグ』があります。
これは、ブランデー30ml、卵黄1個分、砂糖小さじ1杯をカップに入れ、そこに熱い牛乳を入れながらかき混ぜて、最後にナツメグをふりかけるというものです。自分で好みのナイトキャップを作るコツは、疲れを取るためにちょっと甘めにすることです。甘みがあると脳がホッとします。
しかし、美味しいからといって、飲み過ぎないように気を付けなければなりません。小さめのマグカップを使用すれば飲み過ぎは防げるでしょう。

(株)八木酒造部 山丹正宗 バリィさんの寝酒 お土産セット300ml×2 ≪熨斗対応不可≫ お酒 日本酒 愛媛 定番 お土産 老舗 名店 高級 ギフト 贈り物 プレゼント 贈答品 御中元 お中元 お供え物 法要 法事 仏事

